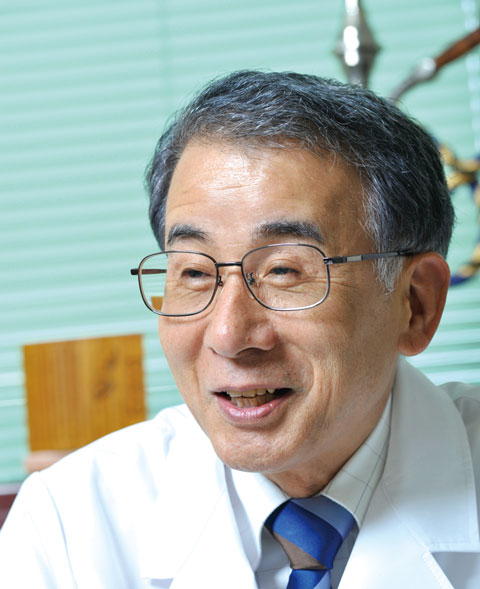【自然療法シリーズ】通仙散と紫雲膏
はじめに
華岡青洲は、全身麻酔薬を創製、応用して世界で初めての乳がん手術に成功しました。
その功績から、外科を通じて人類に貢献した医師のひとりとして米国シカゴにある国際外科学会の栄誉館に、青洲の業績を説明する掲示と肖像画が展示されています。
この乳がん手術の際に用いた麻酔薬が通仙散(別名:麻沸散、麻沸湯)です。
また、青洲は従来からいろいろな中国伝来の処方に創意、工夫を加えて新しい漢方処方、十味敗毒湯や帰耆建中湯、中黄膏などを考案しております。
本稿では通仙散と紫雲膏につきましてご紹介します。
通仙散
華岡青洲は1760年に紀伊国(現・和歌山県紀の川市西野山)に医師の華岡直道の長男として生まれ、1782年から京都に遊学し、吉益南涯に古方派医学を学びました。
次いでカスパル流外科(オランダ商館のドイツ人医師カスパル・シャムベルゲルが1650年頃に伝えた外科技術)および伊良子(道牛)流外科などの蘭漢折衷医学〔漢方(古方医学)と蘭方(オランダ医学)の利点を合わせた医学派〕を学んでいます。
青洲に影響を与えた書物に永富独嘯庵(山脇東洋の門人)の『漫遊雑記』が知られており、そこには「欧州では乳がんを手術で治療するが、日本ではまだ行われておらず、後続の医師に期待する」などの記載がありました。青洲は1785年に帰郷して家業を継いで開業した後、1795年に再上洛して製薬技術の習得に努めたと伝えられます。
当時の麻酔なしの外科手術は、患者には身の毛もよだつ地獄の責め苦であったように思われます。
特に、乳がんは切れば患者の命が危ういとされ、外科治療の対象外といわれていました。
青洲は外科手術での患者の苦痛を和らげて、手術を成功させるためには麻酔薬の開発が必須と考えました。
すでに、中国後漢末期の伝説の名医、華佗(110~207年)は麻沸散を酒とともに飲ませて開胸手術や頭蓋骨の切断手術を実施したと、『三国志』華佗伝や『後漢書』方術伝に記載されていました。
しかし、麻沸散は曼荼羅華(インド大麻ともいわれます)が主剤とされますが処方内容は伝えられておらず、幻の薬でした。
青洲は、「麻沸散」に刺激を受けて曼荼羅華を主剤とした麻酔剤の開発を進め、長い月日をかけて通仙散を完成させました。
その過程で、犬などでの動物実験の後に、延べ十数人の協力者を得て有効性と安全性を確かめており、その中に母親(於継)と妻(加恵)とともに青洲自身も入っていたと伝えられます。
1804年10月、青洲は60歳の女性に対して通仙散による全身麻酔下での乳がん摘出手術に成功しました(しかし、4ヵ月後に患者は死亡)。
その後に青洲が手術した乳がん患者143名のうち、術後生存期間が判明したものだけを集計しますと、最短で8日、最長は41年間生存しており、平均すると約3年7ヵ月になるそうです。
200年以上も前の医療条件下の手術であり、外見から判明できるほどに進行した乳がん患者であったことを勘案しますと立派な治療成績と思われます。
19世紀後半を代表するドイツの外科医C.A.テオドールビルロードでも、有名な1881年に行ったクロロホルム麻酔下での43歳の女性の胃がん切除手術で患者は4ヵ月後に死亡しており、手術後の再発率は80%を超え、3年生存率は4~7%程度といわれています。
青洲の手術は、米国の歯科医師ウィリアムT.G.モートンによるジエチルエーテルでの麻酔手術よりも40年以上前のことであり、青洲の先駆的な手術のすばらしさがわかります。
青洲は門下生の育成にも力を注ぎ、医塾「春林軒」を設け、“内外合一、活物究理”(外科も内科も学ぶべきである、生きているものに真理がある)の精神のもとに生涯に1,000人を超える門下生を育てました。
その中から本間玄調などの優れた外科医を輩出しております。
しかし、青洲には秘密主義的な面があり、門下生たちに通仙散の製造方法の秘密を守る約束をさせていたそうです(これは、通仙散は毒性が強く危険を伴うため、みだりに公開できなかったためといわれています)。
高弟の本間玄調はその著書の中で青洲から教わった秘術を無断で公開したとして破門されています。
また、青洲は自ら著述をしなかったそうで、青洲の著書として伝わるものはすべて門人たちの筆録によるものだそうです。
本間の著書『本間玄調秘授麻薬』1や青洲の著書とされる門人の筆録の薬物書『青嚢秘録』2から、通仙散の処方は、曼陀羅華、草烏頭、白芷、当帰、川芎、天南星(19.5:1.5:1.5:4.5:4.5:1.5、26:3:1:3:3:1)と記されております。
これらの生薬を細かく砕き、水2合で煎じたものを温かいうちに飲むと2~4時間で効果が現れたそうです。

紫雲膏
『古事記』の出雲神話にある因幡の白兎と大国主命の治療物語は日本における薬物療法に関する最初の記録で、いずれも蒲黄や貝の汁を用いた外用薬での治療といえます。
『医心方』(982年、丹波康頼選)には悪性化膿性疾患の廱疽の治療に外用療法が記載されており、南北朝の戦乱時代に外科として金創治療が発達して膏薬が用いられました。
安土・桃山時代に外科は金創と瘍科(瘡科)に分かれて、江戸時代には多種多様な膏薬が現れました。
青洲も中国の十四陣法の名称にちなんだ名前の膏薬を計25種開発しております。
紫雲膏はそのひとつで、中国の明時代の外科医、陳実攻の著した『外科正宗』にある潤肌膏における紫根の量を6倍にし、豚脂を加えた処方です。
ひび、あかぎれ、かぶれ、火傷、切り傷、凍瘡、褥瘡、痔の治療に用いられます。
当時の処方は紫根、当帰、香油(ゴマ油)、黄蝋、豚脂(6:5:40:6:1)ですが、今日、企業によって配合比率が異なっております。

初出:特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会会報誌『 MEDICAL HERB』第40号 2017年6月